弔電の送り方|いざというときのために知っておきたい手順とマナー
社会人になると、弔電を送る機会が訪れることがあります。弔電とは、亡くなった人への弔意を電報の形で遺族に伝えるもので、葬儀に出席できないときによく利用されます。
では、いざ弔電を送るとなったとき、どのように手配し、どんな文面にするのがいいかご存じでしょうか。
弔電を利用する際は、遺族に失礼がないよう、送る日時や文章などのマナーに配慮することが大切です。
今回は、弔電を利用したことがない人にもわかりやすいように、弔電を送る手順とマナーをご紹介します。
弔電を送る手順
 弔電は通夜や告別式に参列できない場合に、お悔やみの気持ちを伝えるものです。どちらかに参加できる場合は、弔電を用意する必要はありません。
弔電は通夜や告別式に参列できない場合に、お悔やみの気持ちを伝えるものです。どちらかに参加できる場合は、弔電を用意する必要はありません。
家族葬の場合や、「香典・供花・供物は辞退いたします」といった案内がある場合、弔電は送っても問題がないとされています。
弔電には電話注文や郵便局、インターネットで申し込む方法があります。
電話で注文する場合は115番にかけて、オペレーターとやりとりをしながら文面や台紙などを決定します。19時までに申し込めば当日に配達してくれるので、緊急時に便利なのがメリットです。
郵便局で申し込む方法には、手書きの文字を送れたり、追跡サービスで配達状況を確認できたりするメリットがあります。
電話をかける時間がない人や、送る前に完成形のプレビューを確認したい人などには、インターネットからの申し込みがおすすめです。画面上で弔電の台紙を選ぶことができ、文章も例文を参考にしながら記入できます。
インターネットでの申し込み手順
申し込む前に必ず、通夜や告別式の日時と式場、喪主の氏名を確認しておきましょう。
インターネットでは、まず台紙を選びます。次に、申し込みフォームに従って自分の連絡先や送り先の住所、送る日付、時間帯、喪主の名前などを入力します。確認後はお悔やみの文章を入力し、最後に支払い情報を入力すれば、申し込み完了です(サービスによっては会員登録があるなど、順番が前後することがあります)。
配送や申し込み締め切りは、商品や届け先によって異なります。届け先が遠方の場合は、早めに手配するようにしましょう。
困ったときは文例を活用
お悔やみの言葉がうまく書けないときは、文例を参考にするのも一つの方法です。また、仕事の取引先に送るときや、それほど付き合いが深くない場合なども、電報サービスに用意されている文例を関係性に応じて選ぶと良いでしょう。
弔電を送る際のマナーとは
弔電を送る際、気を付けたいマナーがいくつかあります。形に残るものなので、特に「忌み言葉」の使用には注意しましょう。
弔電を送るタイミング
斎場に送る場合は「通夜の前まで」が基本です。もし通夜に間に合わないようであれば、弔電が披露される告別式に間に合うように手配します。
通夜が自宅で行われるときは、自宅に直接弔電を送ります。その場合は、受取人となる遺族が通夜の準備に追われている可能性もあるため、通夜の直前に弔電が届かないようにします。
宛名(受取人氏名)
弔電の宛名(受取人氏名)は一般的に喪主の氏名を記入します。万が一、喪主の名前がわからない場合は「○○家 ご遺族様」というように故人の家族宛てにします。
あらかじめ「様」が印刷される場合は入力フォームに注意事項が書かれています。「○○様 様」とならないよう入力時に注意してください。
差出人名
差出人の部分に氏名しか記入されていないと、故人と差出人の関係性がわかりません。遺族に余計な手間や気遣いを増やさないためにも、氏名とともに故人との関係性をわかるように明記します。
例えば、会社関係であれば「株式会社○○ 営業部~」というように、会社名と部署名、肩書きを併せて記入しましょう。プライベートであれば、「○○学校 ○年卒業~」「○○学校 ○○クラブ 会長~」などと記載します。
忌み言葉を使わない
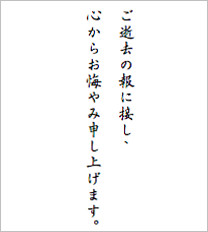 弔電のメッセージには、不幸が重なったり繰り返されたりすることを連想させるような言葉や直接的な表現を使わないのがマナーです。訃報を受けた際のやりとりや葬儀会場での会話においても、忌み言葉の使用を避けます。
弔電のメッセージには、不幸が重なったり繰り返されたりすることを連想させるような言葉や直接的な表現を使わないのがマナーです。訃報を受けた際のやりとりや葬儀会場での会話においても、忌み言葉の使用を避けます。
不幸が繰り返し起こるのを連想させる言葉
「再び」「引き続き」「追って」「追いかける」「次に」「またまた」「重ね重ね」「重々」「次々」「いよいよ」「ますます」「つくづく」「返す返すも」など
音が不吉とされる文字
「四」「九」など
直接的な表現
「死ぬ」「死亡」「自殺」「急死」「ご存命中」「生きている」など
弔電が葬儀に間に合わなかった場合
お通夜にも告別式にも弔電が間に合わなかった場合、弔電またはお悔やみの手紙を初七日までに送ります。電話で後日あらためて弔問に伺う旨を話しておき、直接お悔やみの言葉を伝える方法もあります。
早すぎる弔電の手配も避ける
斎場に早く弔電が届きすぎるのも、遺族や斎場の迷惑になりかねません。届かなかったり受け取ってもらえなかったりするのを防ぐためにも、葬儀の日時はきちんと確認しましょう。
弔電の種類
インターネットから弔電を申し込むと、豊富な種類の弔電台紙やギフトタイプの弔電の中から、好きなものをパソコンやスマートフォンの画面上で選べます。一般的には次のような種類の弔電があります。
種類
台紙
 最も一般的な厚紙を使用した弔電です。蓮を描いたものや、そよ風をイメージしたもの、水面を描いたものなど、さまざまなデザインがあるので、送る相手に合わせてセレクトします。価格が安く設定されているので、関係性があまり深くない人など、お付き合いや形式的に送るときに利用されることが多いタイプです。
最も一般的な厚紙を使用した弔電です。蓮を描いたものや、そよ風をイメージしたもの、水面を描いたものなど、さまざまなデザインがあるので、送る相手に合わせてセレクトします。価格が安く設定されているので、関係性があまり深くない人など、お付き合いや形式的に送るときに利用されることが多いタイプです。
布張り電報
電報の表紙に布を使用した上品なタイプで、台紙タイプの電報よりも重厚感があります。故人がお世話になった上司の場合、あるいは差出人がある程度の役職に就いている場合などにおすすめです。
刺繍電報
花の刺繍が施された、上品さと高級感のある電報です。価格は5000円前後と比較的高めですが、故人との関係性が深い場合などに向いています。
高級電報
電報の中には銀の箔押しが入っている高級タイプのものがあり、金沢の銀箔を全面に施した1万円以上の最高級電報もあります。故人が特別な人の場合に、送ると良いでしょう。
キリスト教向け電報
キリスト教を信仰している人に送る電報です。送る文面には「供養」「冥福」「成仏」「ご愁傷様」などの仏教用語が使えないので、注意しましょう。
お供えセット電報
故人やご家族と親しく、弔電とともにちょっとした供物を送りたいときに重宝します。線香やろうそく、お焼香などがセットになったものがあります。
選ぶ際のポイント
 相手へのメッセージが形に残るのは手紙も同じですが、電報には手早く簡単に届けられるというメリットがあります。電話・インターネットで申し込む場合、台紙を選んでメッセージや必要な情報を伝えるだけで、発送する手間がかかりません。
相手へのメッセージが形に残るのは手紙も同じですが、電報には手早く簡単に届けられるというメリットがあります。電話・インターネットで申し込む場合、台紙を選んでメッセージや必要な情報を伝えるだけで、発送する手間がかかりません。
また、当日届けてもらえるサービスもあり、緊急の際に便利です。業者によっては、海外からの申し込みや海外への送付も可能です。
台紙のデザインやギフトによって、手紙よりも特別な形でメッセージを送ることができるのも電報の良いところです。記念品として大切にしてもらえるでしょう。
電報の主な利用法
基本は故人との関係や自分の立場で選びます。それほど付き合いが深くなければ、1000円~2000円くらいの台紙で良いでしょう。
親しい友人や同僚の両親、配偶者の葬儀の場合、本来お葬式に参列するときに持って行くはずだった香典と同程度の金額のものを選びます。
故人や遺族ととても親しく、参列できないお詫びの気持ちを伝えたいときには、お供えとセットで送る電報がおすすめです。
会社や団体として弔電を手配する際は規定に従うか、上司に指示を仰ぎます。
文字数で料金が変わらない電報サービスがおすすめ
電話で申し込むタイプの電報では、文字数に応じて細かく料金が設定されています。一方、民間の電報サービスでは、料金体系が文字数換算になっていないタイプが多く見られます。
文字数によって料金が変わらないサービスでは、300文字など文字数に上限があるものの、ある程度の文量であれば気にせずに書くことができます。
マナーを守って悼む気持ちを伝えましょう
通夜や告別式に参列できないとき、悲しみの気持ちを伝えられるのが弔電です。必ず送らなければならないものではありませんが、故人と関係が深かった場合などは、送るのが礼儀でしょう。葬儀に参列できなかった人から弔電を受け取ると、その人が故人の死を悼んでいる気持ちを、遺族も知ることができます。
せっかく弔電を出すなら、間違いはなくしたいもの。いざというときに慌てないためにも、今のうちからマナーを覚えておくと安心です。


